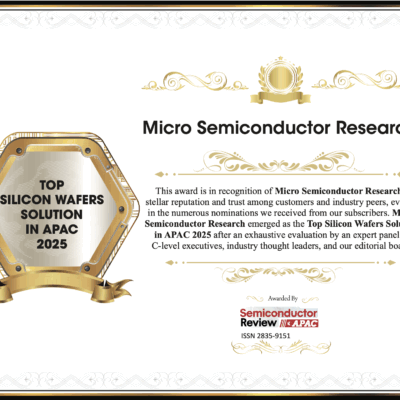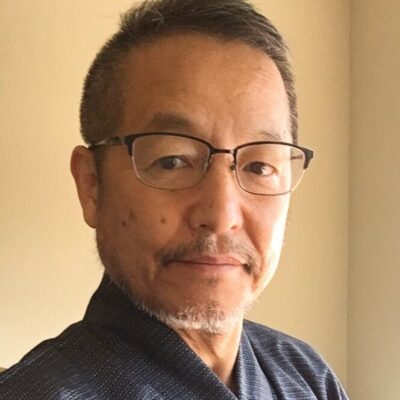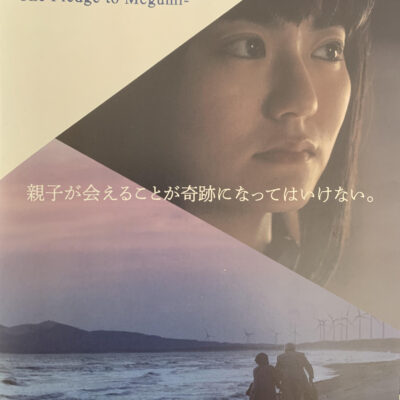日本の国の成り立ちを考える
日本人って勤勉で働き者で、さらに言えば技術力は高く常にいいモノと作くろう考えている
、、、と思う。
一方西洋人は新たなモノを作るのだがそこから先への進化があまりない
、、、と思う。
そしてアジア人はモノ作りをする国もあるのだが、所詮はモノマネから脱却できない
、、、と思う。
どうもこれは国の成り立ちに関係しているのではないか
、、、と思う。
日本以外の国々の国の成り立ちについては勉強したことがないので、今回は考察はしないが、日本の国の成り立ちを考えてみた。
ボクはよく古事記を引き合いに出すが、やはり古事記から得る情報はボクにとっては重要だ。いろいろな出来事を物語風に綴っているのでその本質を見定めると面白い事柄が現れる。古事記は物語ではなく歴史書だ。物語として書かれているが、全てが暗号だ。
さて、いろいろな出来事が古事記にはあるが、天孫降臨と国譲りに着目して考えてみよう。
天孫降臨
天孫降臨は高天原から葦原中国に天照大神の孫にあたる邇邇芸命を派遣して葦原中国を治める出来事である。
高天原から葦原中国へ天照大神の命を受けて派遣しようとした最初の神はアメノオシホミミ神だったが天つ橋から葦原中国を眺めた時に騒々しいと言って途中で高天原に帰ってしまう。
この騒々しいというのはどう言う状態だったのか?
これは欲望が満ち溢れている欲望の塊なのである。自分の欲を満足させるためには人からどれだけ奪っても構わない、自分を守るためには相手に奪われないようにしないといけないと思うため、しゃべりまくるし要求しまくりお互いにみんながそれをやっているので騒々しいとなるわけである。騒々しい国や社会はみんなが欲望の塊となり欲望に支配されて富を奪い合っている。少しでも自分の取り分を増やそうとしてみんながギャーギャー大騒ぎしている状態。これを騒々しいと言うわけである。欲望の渦巻いている葦原中国を天照大神はこれではダメだということでアメノホヒ神を遣わすが大国主神に従ってしまう。次にアメノワカヒコ神を遣わすがまたまた高天原に帰らず高天原から射た矢に当たり死んでしまう。最後にアメノオシホミミの息子である邇邇芸命ー天照大神の孫ーが派遣された。
これを天孫降臨といい、日本の統治を根底から改めさせるために葦原中国に派遣させたのである。
小名木善行:古事記から読み解く経営の真髄より
邇邇芸命と国譲り
日本の国の成り立ちを紐解けば、天孫降臨と国譲りが大きな要素である。
天照大神の命をうけて天孫降臨した最後の神様は邇邇芸命と言う。
- 「邇」とは近いという意味でこれが重なり「邇邇」とは非常に近いとなる。
- 「芸」とは技術という意味で「身近に技術を置く社会」
それまでは大国主命が交易をして富を稼いでおり、その富を分配することで国を治めていた。しかし人が増えることにより富の分配では成り立たなくなり、結果として騒々しい国となったのである。
ここで邇邇芸命の登場によりそれまで交易をしていた大国主命から国譲りをして、技術を身近におく社会を作り、ここからモノつくり国家、技術立国をめざしたのである。
小名木善行:技術大国「日本」はここから始まったより
五伴緒神(いつとものおのかみ)
邇邇芸命が天孫降臨したときに一緒に連れてきた五柱の神々がいた。
この神々を五伴緒神(いつとものおのかみ)と言う。
- 伴とは技術集団という意味
- 緒とはその集団の長という意味
五つの神の緒にはその背後に技術集団が共に天孫降臨したのである。その五つの集団とは;
- 天児屋命(あめのこやのみこと):大工・土木建設の神
- 布刀玉命(ふとだまのみこと):飾り職人の神
- 天宇受命(あめのうずめのみこと):芸能の神
- 伊斯許理度売命(いしこりとめのみこと):金属加工の神
- 玉祖命(たまのおやのみこと):精密機器加工の神
そして大国主命が治めていた商業立国から技術立国へと国譲りをしたのである。
小名木善行:技術大国「日本」はここから始まったより

これが日本の国の成り立ちだ。日本は神話の時代からすでにモノ作り国家、技術立国をめざしていたのだ。なるほど、日本が性能が高く信頼性があり故障しないモノ作りをしてきたのは、遥か太古の昔からだったのだ。古事記といえば千三百年前に編纂された書物で、その時点ですでに古事記なのだ。神話と前述したが、実はこれは紛れも無い歴史書なのである。
日本人の遺伝子に受け継がれているこのモノ作りは今後も絶えることなく受け継がれていくことだろう。
了