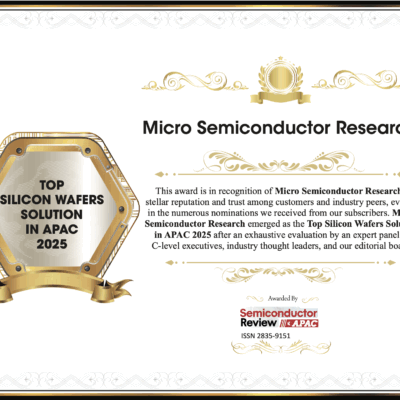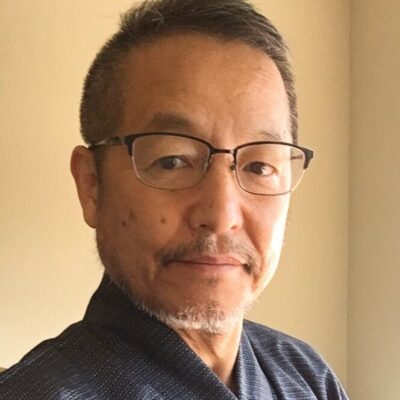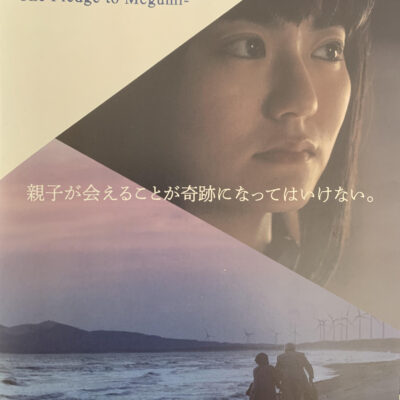人工知能AIについての考察
ChatGPT始め多数のAIアプリケーションが巷を賑わせている。なんでもかんでもAIに聞いて判断する輩も自分の周りにはたくさんいる。そういう自分もChatGPTを活用している一人でもある。
AIについては以前にもブログに書いているので参照していただければ、と思う。
https://www.yamashitaseiji.jp/bill/435/
AIを馬に例えるならば、AIに乗って手綱を引き自分の意思通りに馬を走らせることが出来る人間になるのか、それとも馬に引きずられてどこへ行くのかも知れずの人生を送るのか、という問いを投げかけた。
https://www.yamashitaseiji.jp/bill/438/
AIの発展と共に労働者への恐怖を与えることを懸念し、AIが世界にもたらす可能性の高いリスクはAIが何らかの文明の破局をもたらすことでも、雇用に大きな負のショックを与えることでもない。むしろ、効果的な指針がなければ、AIによるイノベーションは今後何世代にもわたって世界経済の強化をもたらすのではなく、現在の経済格差を単に拡大するような方法で開発・実施される可能性があるということだ、というAIのもたらす影響について考察した。
https://www.yamashitaseiji.jp/bill/441/
人間と人工知能の臨界点であるシンギュラリティ。人間が考えられる領域を超えた時に誰があるいは何がシンギュラリティを管理するのか?その時人類同士の戦争はなくなりシンギュラリティそのものがが抑止力となるのではないだろうか?という技術が抑止力になりえるのか、という問題に関してまとめた。
ボクは仕事の関係上弁護士先生との打ち合わせもあり、要求される提出書類もある。この要求される書類をChatGPTに問い合わせ作成してみた。多少手直しする部分はあるものの結構素晴らしい書類ではないか、と思うほどの出来栄えだった。このような書類を自分の能力だけで書けるものなのか、と思うほどだ。なるほど、これは使える。
このようにAIはあたかも問いに対して答えを出してくれる玉手箱なのか、と思わせる。そこで以前のブログでも書いたのだが、その一部を抜粋すると;
「筆者は半導体産業の仕事に従事していて、その一つに半導体製造装置メーカーをサポートする仕事がある。装置の搬入据付作業から保守メンテナンス作業のサポートをしている。装置に問題が発生すると夜中でもクリーンルーム(半導体工場のことを業界ではクリーンルームと言う)へ直行し保守を行うのである。このような仕事をしていてAIが応用できないものだろうか、と考えた。問題の多くの原因は複雑な装置を取り扱う作業員に起因していることが多い。装置はPLC(Programable Logic Controller=プログラム可能な演算処理機)によって制御されている。あらかじめ取扱説明書に記載されている内容で作業が行われその通りに装置がPLCにより仕事をするのである。しかし予期せぬ作業をしたときに装置は想定外の作業が行われるのでPLCでは制御不能に陥る。そうすると夜中だろうが構わず連絡が入りクリーンルームへ行くのだ。その間装置は停止したままなので生産が停止し、また筆者も寝ているところを起こされるので、楽しい夢を見ているところを遮断される。いやいや行くので生産性が上がらない。
生成型AIを使えば想定外の作業がなされたときにPLCをAIが自動でアップデートして問題解決ができるようになる可能性があるのではないか、と考えた。装置はその時々に起こった状況を逐次記録している。専門用語で「ログ」と言う。問題が発生した時点で起こったログをAIが解析し、そしてPLCプログラムを自動で再構築することができれば、まさに生産性向上につながる。半導体メーカーも保守メンテナンスに関わる費用を大きく削減することができる。装置メーカーはあまり利益にならない保守メンテナンスを縮小し、その時間は新規装置の開発や装置の製造へ人員配置ができる。労働力が低下している日本では大きな効果が期待できる可能性を秘めている。
なるほど、たしかに生成型AIによる経済的効果だ。」
このような可能性を記した。その後AIの展示会に行き数社の専門家に上記を問い合わせてみたところ、あらかじめPLCにプログラムしていたプログラムがあって、問題が発生したときにそのプログラムを自動で追加することはできるがプログラムを作ることはできない、との事だった。これでは何もならない。あらかじめプログラムする、ということはそのような問題が発生するであろうとプログラマーは認識しているので、であればそのプログラムを最初から装置に構築しているので、何の解決にもならないことを学んだ。
結局AIというのは膨大なデータベースがあって、個人個人の知り得る部分はほんの一部で知り得ない部分を回答するのであたかもAIが考えて教えてくれる、という錯覚なのではないか?
AIの「A」はArtificialで人工物、自然のモノではない、という意味だ。人工物である以上AIがヒトを超えることはない、というのがボクの持論である。
先日AIについて3人でランチをしながらシリコンバレーで議論した。一人は最大手半導体製造会社のレバノン系アメリカ人、もう一人は半導体業を専門とするベトナム系アメリカ人とボク。
ベトナム系はプレゼンテーション資料等一切の書類作りと情報をAIを最大限活用しているようで、今後はあらゆる仕事はAIに置き換えられる、と信じて疑わない勢いだ。半導体の設計もなにもかもAIができる。と言う。半導体製造においては常に新たなプロセスが生み出されそれに対応した製造装置の設計は人間でなければできない、というのがボクの意見だったが、それもAIができる、と言う。
レバノン系は概ねベトナム系に同意してはいるもののボクの意見もあるところでは聞いていて笑みを浮かべていた。
ボクはArtificial(人工物)である以上、その向こうにはAIは到達できない、と主張する。ただし人間とAIの臨界点(があったとして)に達したときどうなるのかは不明だ、と議論した。
感じた事なのだが、レバノンはイスラエルの北に位置する地中海東部の国家だ。豊かな歴史を持ち、宗教的・民族的な多様性を持つ文化的アイデンティティを形成してきた。レバノンの文明の最も初期の証拠は、記録された歴史によれば7000年以上前に遡る。また日本民族との共通点はある。
一方ベトナムは漢・唐の時代には中国の侵略に抵抗できず、チャイナからの直接支配を受けた。19世紀後半にはフランスが中国の清王朝を破り、ベトナムを中国の冊封体制の下から転出させて、フランス領インドシナという植民地政府の下に編入した。
AIに委ねられるベトナム系とボクの意見に笑みを浮かべるレバノン系、そしてAIはあくまでもArtificialであるとい言うボク。